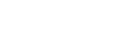訪船のため出張。
Interview
Akari Ishii
GHG削減に向けて、
その戦略と新規案件発掘を
技術部門として支える。

技術
石井 明莉
環境・技術戦略グループ
環境・技術戦略チーム
2021年新卒採用
(2023年取材当時、入社3年目)
Profile
海運業界、航空業界を中心に就職活動を行い、その中でも面接を通して知った風通しの良い社風に惹かれて、当社に入社。
入社後、先進技術開発チームに所属し、3つのプロジェクトに携わる。現在は環境・技術戦略グループ 環境・技術戦略チームに所属している。

01
大学時代に
学んだ知識を生かして、
巨大な船の安全運航に
貢献したい。
Q. 海運業界を志したきっかけは?
私が生まれ育った地域は全国的に見ても交通事故が多く、身近な人が交通事故にあった経験もあり、自動車の安全分野に興味がありました。そのため大学時代は自動運転車の研究を専攻。
研究を進める中で、より大きな乗り物であれば社会的なインパクトも大きいということに気がつきました。
船など大型の乗り物の安全運航に自身の知識を生かしたいと思い、就職活動をスタートしました。
Q. その中でも当社へ入社を決めた理由は?
1つ目の理由は、面接時の話しやすさ。
オンライン面接は社員の方が面接官だったのですが、私のこれまでに興味を持ってくださり、真摯に聞いてくださいました。一人ひとりの個性に興味を持って、フランクに話しかけてくださる社員の方が多く、このような方と一緒に働きたいと思えたことが決め手です。
2つ目の理由は、社内の多様な部署・部門で経験が積めること。当社にはジョブローテーション制度があるため、技術職で入社しても営業やオペレーション、チャータリングなどを学ぶことができます。技術職以外の経験を積めることや海運について幅広い業務知識を得られることが大きな魅力だと感じました。
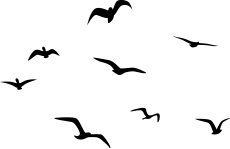
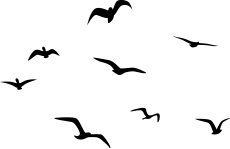


02
様々なプロジェクト経験で
得た知見のもと、
当社、そして業界の
課題解決に貢献していく。
Q. 入社後からこれまでの歩みを教えてください。
入社後、現場研修や、船の構造についての講座などを経て、半年後には液化CO2輸送プロジェクトと、自動運航プロジェクトに携わりました。初めは専門用語も多く、わからないことばかり。そんな中、自主的にインプットする時間も設け、勉強と実務を通して知識を増やせたことが財産になっています。
業界全体の高齢化問題を見据えた自動運航プロジェクトでは、大学時代の研究知識も生かしての説明資料作成や、現場のサポートを担当。船乗りとして現場経験のある方が上司だったため、開発している技術が現場でどのような影響を及ぼすのかを丁寧に話してくれ、この技術が川崎汽船だけでなく、業界全体の未来にもつながっていくと思うと気が引き締まりました。
さらにその後は、当社としても力を入れている、環境にも配慮した運航をするための風力補助装置、Seawingプロジェクトに参画。すでに船への搭載は進んでいる中、実用のための準備段階に携わり、大きなやりがいを感じました。
そして現在は環境・技術戦略グループ 環境・技術戦略チームに所属し、技術部門としてその戦略立案や新規案件の発掘を支えています。
Q. 仕事に取り組む上で大切にしていることは何ですか?
新しい技術や情報のインプットの時間を1日の中で欠かさずに設けることです。
それは入社時に上司から「新しいことを探すマインドが大事だ」と教えてもらったことがきっかけです。最先端技術は1日1日アップデートされていくため、船に使えそうな新しい技術のリサーチを欠かさないよう心がけています。
チーム内で業界紙を読み合う文化があるため、その中で気になった展示会や技術発表会には積極的に参加し、また船とは関係ない分野の展示会にも訪れ、船に転用できる技術はないかを日々検討しています。
今働いていて感じるのは、会社説明会で教えていただいた「“K”LINEスピリット」を、社員一人ひとりが体現しているということ。
縦横の関係は風通しが良く、上司に仕事の相談はもちろん、わからないことも聞きやすい環境が整っています。若手からの提案にも快く耳を貸してくれるので、提案が通り案件として進めていくことも多々あります。
これからの目標は新たな技術開発を検討し、実用までを見届けること。会社の課題はもちろん、業界全体の課題解決にも貢献したいと思っています。
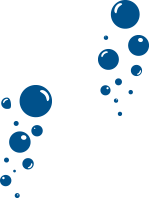
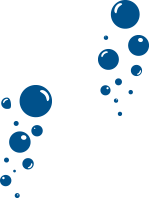
一日のスケジュール
Schedule
-
9:00
-
10:00
搭載したシステムの見学をする。
-
12:00
昼食、船員たちと雑談。
-
13:00
船員たちの作業に立ち会う。
-
15:00
小休憩。船員たちに最近の困りごとを聞く。
-
17:00
下船し、帰宅。
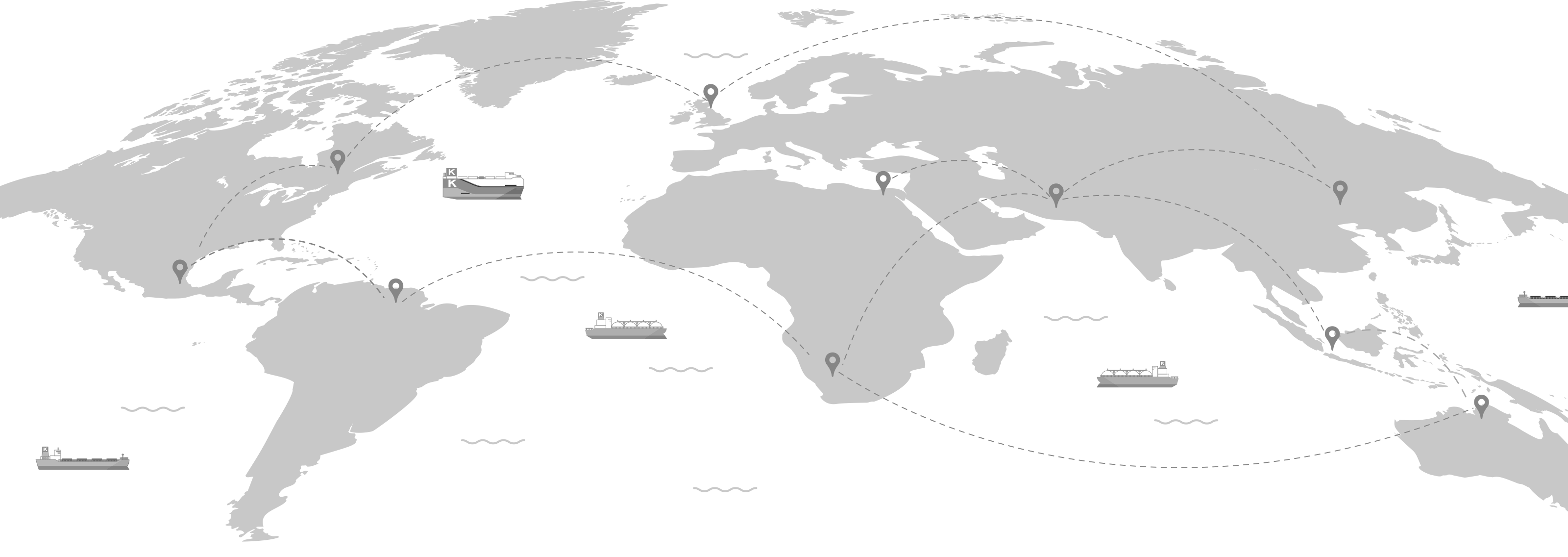
私の世界の“つなぎ方”

現在の業務の中では、国内外問わず様々な企業と、脱炭素について意見交換する機会が多くあります。国も年代も幅広いですが、脱炭素という同じ目標に向かって、熱く議論している時、世界とつながっていると感じます。
そんな中、GHG削減戦略について一緒に取り組むパートナーが何を望んでいるのか、言葉の先にある意図も意識することが、世界のGHG削減の実現に少しずつつながっていくのだと思っています。